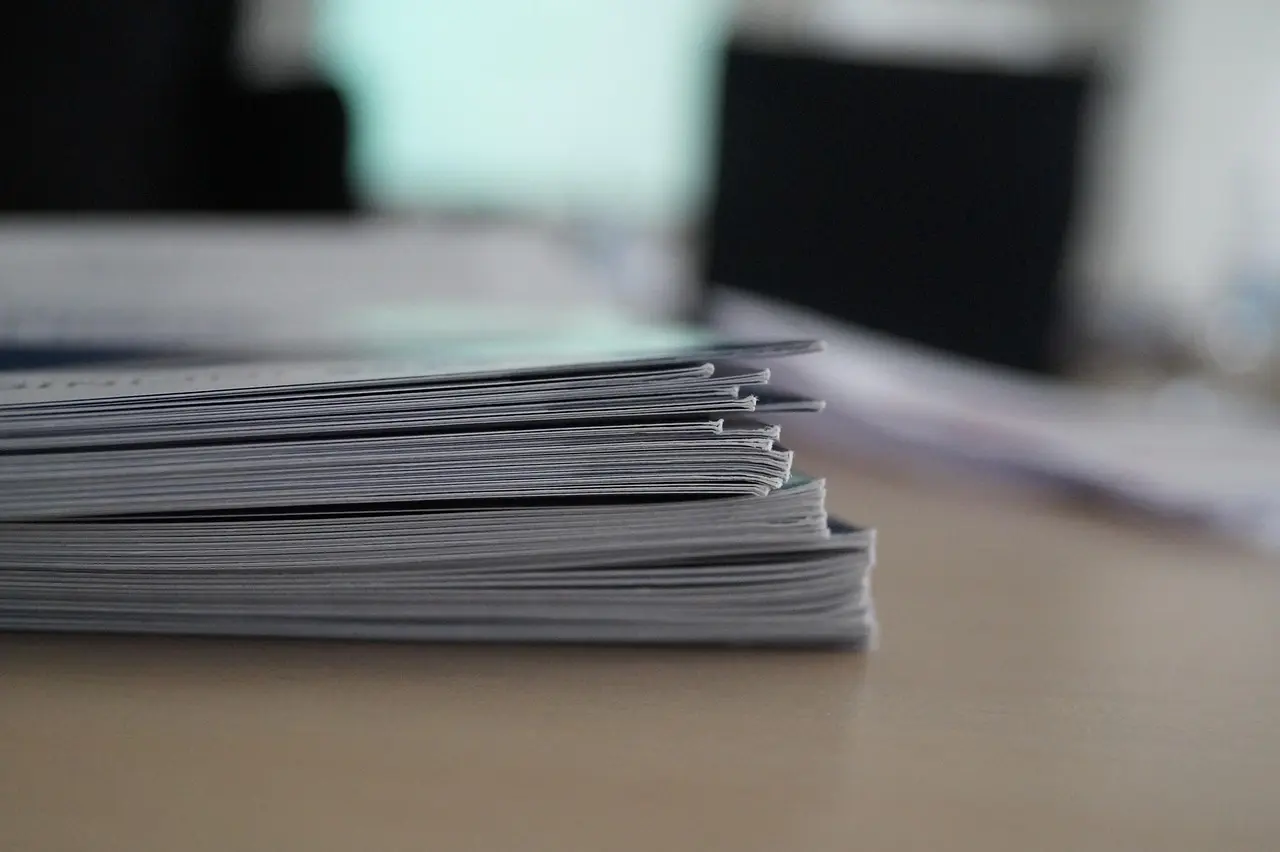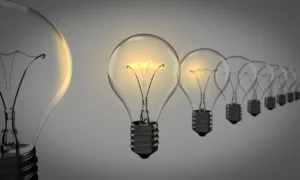近年、「ハラスメント」という言葉は職場や日常生活において広く認識されるようになりました。セクハラ、パワハラ、モラハラなど、さまざまな種類のハラスメントが問題視されていますが、「ホワイトハラスメント」という言葉を聞いたことはありますか?
これは一見すると悪意がないように見えながら、実際には相手を不快にさせたり、精神的な負担を与えたりする厄介なハラスメントです。本記事では、この「ホワイトハラスメント」の正体と、その特徴、そして具体的な対処法について詳しく解説します。
ホワイトハラスメントとは?
まずは「ホワイトハラスメント」について簡単にを見ていきましょう。
ホワイトハラスメントの基本的な定義
ホワイトハラスメント(略称:ホワハラ)とは、上司や先輩が「配慮」「優しさ」の名のもとに、部下や新人社員への仕事や責任の割り振りを極度に控え、結果的に相手の成長機会ややりがいを奪ってしまう職場内ハラスメントの一種です。
例えば、
- 「私がやるから、あなたはやらなくていい」
- 「残業しなくていいよ」
- 「もっと簡単な仕事だけでいいよ」
など、「善意」で業務や負担を抑える配慮が、かえって部下のモチベーションやキャリア形成の妨げになる事例が増えています。
ホワイトハラスメントが生まれる背景
昨今、パワハラやセクハラなど従来型のハラスメントへの社会的意識が高まる中、多くの管理職が「ブラック」上司と見なされることを恐れ、指導を控える傾向が強くなりました。
その結果、上司があえて厳しい業務を振らない、もしくはネガティブフィードバックをしないことが「新たな問題」として認識され始めています。
特に若手社員は「成長できる環境」を求める傾向が強いため、「任せてもらえない」「挑戦させてもらえない」と感じると、早期離職につながるケースもあります。
ホワハラの具体的な事例
| 事例 | 問題点 |
|---|---|
| 上司が「やらなくていい」と仕事を巻き取る | 本人が経験する機会を奪い、成長を阻害 |
| 過度な手助けで本人の判断機会を奪う | 「自分でやるべきだった」と無力感につながる |
| 難易度が低すぎる仕事しか任せない | スキルアップやモチベーションの低下 |
ホワイトハラスメントはパワーハラスメントの一形態だった
なぜ“ハラスメント”なのか?――パワハラとの関係
ホワイトハラスメントは「優しすぎる/過剰な配慮」が原因で、部下のやりがいや成長につながる経験や責任を取り上げてしまう形のハラスメントです。「あなたはやらなくていい」という“思いやり”によって、受け手がチャンスや動機を失うのが特徴です。結果として、本人の意思に反して仕事を任せない・指導しないなどが該当します。
一方、パワーハラスメントは「優越的な関係」を利用した、精神的・身体的な攻撃(暴言、無視、過剰な指示・叱責など)や合理性のない業務命令を行う行為が典型です。厚生労働省の定義では「優越的な関係」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為」「就業環境の害」の3要件を満たすものが該当します。
| 項目 | ホワイトハラスメント | パワーハラスメント |
|---|---|---|
| 主な特徴 | 過剰な優しさ・配慮で成長機会を奪う | 優越的立場を背景に精神的・身体的な攻撃や過度な要求・指導を行う |
| 代表的な行為 | ・簡単な仕事しか与えない ・積極的に指導しない ・本人に配慮しすぎて仕事を任せない | ・暴言や無視、過剰・過小な要求 ・人間関係からの切り離し ・個人の尊厳を傷つける行為 |
| 背景 | ハラスメント配慮の過剰反応や指導忌避 | 権限や役職、立場の力関係 |
| 法的扱い | パワハラの「過小な要求」に該当することが多い | 労働施策総合推進法等で6つの類型として規定 |
| 受け手への影響 | 成長の機会喪失、無力感、モチベーション低下 | 就業環境の悪化、精神的・身体的な苦痛 |
「過小な要求」と呼ばれる「本来の能力以下の仕事しか与えない」「仕事を任せない」といった行為が、いずれもパワハラの一類型とされています。ホワイトハラスメントの場合は“善意”が動機である点が特徴です。
ホワイトハラスメントを防ぐポイント
下記はホワイトハラスメントを防ぐためのポイントです。
- オープンなコミュニケーション
上司と部下が日常的に希望や意見を話し合い、お互いの期待値と現状を明確に共有する。 - 具体的かつ建設的なフィードバック
単なる「優しさ」だけでなく、本人の努力や課題、強みと改善点を明確に伝える。 - 仕事や役割の適切な配分
経験や能力、成長意欲に応じて裁量や責任を徐々に与えることで「挑戦する機会」を設ける。 - 本人の意思を尊重したサポート
必要なときにだけ手助けし、自己判断や自主性を育てる。 - 相談しやすい職場環境の整備
問題や違和感を自由に話せる雰囲気と、匿名で意見を出せる仕組みを設ける。
実際の企業の対応や工夫
| 取り組み | 詳細内容 |
|---|---|
| 1on1ミーティングの実施 | 上司と部下が定期的に1対1で話す場を設け、成長課題や希望をヒアリング。 |
| フィードバック制度 | 日常的な声かけや評価面談を通じて、チャレンジも失敗も公平に認める文化を醸成。 |
| 教育・研修の強化 | 管理職向けに配慮と成長機会のバランスを取る指導法、ハラスメント防止教育を実施。 |
| 役割分担の見直し | メンバーのキャリア志向やスキルを可視化し、業務やプロジェクトの割り振りを客観的に行う。 |
| 外部窓口や匿名アンケート | 外部相談窓口や匿名アンケートで、本人が直接言いづらい意見や課題も把握する仕組みを導入。 |
これらのポイントと工夫によって、「善意が裏目に出る」状況やモチベーション低下を防ぎ、個々が自分らしく成長できる職場づくりが進みます。
まとめ
「ホワイトハラスメント」とは、パワハラやモラハラといった従来型のハラスメントとは逆ベクトルの、「行き過ぎた優しさ」が職場の成長や活力を奪う、新たなハラスメントです。
相手がどう受け止めるか、どのようなニーズや希望を持っているのかに寄り添うコミュニケーションが、職場の良好な関係と本人の成長の双方を支えるカギです。
(参考サイト)あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-(厚生労働省)